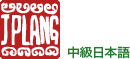-
食生活
しょくせいかつ
 生活の中で、食事に関係がある部分
eating habits
生活の中で、食事に関係がある部分
eating habits
-
国々
くにぐに
 たくさんの国
countries
人々、日々、家々、山々
たくさんの国
countries
人々、日々、家々、山々
-
主食
しゅしょく
 ふだんの食事の中で主な食べ物 (例:米やパンなど)
a staple food
ふだんの食事の中で主な食べ物 (例:米やパンなど)
a staple food
-
副食
ふくしょく
 主食といっしょに食べるもの (例:魚や肉や野菜など)
dishes other than the staple food
主食といっしょに食べるもの (例:魚や肉や野菜など)
dishes other than the staple food
-
分けて・分ける
わけて・わける
 [を][に]
一つのものを、二つ以上のものにする
to separate
売り場が分かれている
[を][に]
一つのものを、二つ以上のものにする
to separate
売り場が分かれている
-
日常
にちじょう
 毎日のこと;ふだん
daily; ordinary; usual
毎日のこと;ふだん
daily; ordinary; usual
-
中心
ちゅうしん
 まんなかのところ;大切なことや大切なもの
center; basis
まんなかのところ;大切なことや大切なもの
center; basis
-
~となる
~となる
 ~になる
~になる
-
穀物
こくもつ
 米、麦、豆、とうもろこしなど、主食になる植物
grain; cereals
米、麦、豆、とうもろこしなど、主食になる植物
grain; cereals
-
(穀物)とともに
(こくもつ)とともに
 (穀物)といっしょに
together with (grains)
(穀物)といっしょに
together with (grains)
-
おかず
おかず
 副食
dishes accompanying the rice
副食
dishes accompanying the rice
-
食文化
しょくぶんか
 食事の習慣に関係のある文化
food culture
食事の習慣に関係のある文化
food culture
-
食文化圏
しょくぶんかけん
 世界の国の中で、食文化が同じような地方のグループ(group)
food culture area
世界の国の中で、食文化が同じような地方のグループ(group)
food culture area
-
アジア
アジア

-
諸国
しょこく
 いろいろな国
countries
いろいろな国
countries
-
(アジア諸国)と同様
(アジアしょこく)とどうよう
 (アジア諸国)と同じように
(アジア諸国)と同じように
-
米食
べいしょく
 米を主食として食べること
rice eating; living on rice
米を主食として食べること
rice eating; living on rice
-
既に
すでに
 もう
already
もう
already
-
時代
じだい
 歴史を、ある特徴から分けた長い時
a period
歴史を、ある特徴から分けた長い時
a period
-
弥生時代
やよいじだい
 B.C.300~A.D.300年 ☆日本の歴史の時代の名前 ☆この時代に米を作り、銅などの道具を使った
the Yayoi Era
B.C.300~A.D.300年 ☆日本の歴史の時代の名前 ☆この時代に米を作り、銅などの道具を使った
the Yayoi Era
-
古くは
ふるくは
 古い時代は;昔は
in ancient times
古い時代は;昔は
in ancient times
-
肉食
にくしょく
 肉を食べること
meat eating
~する
肉を食べること
meat eating
~する
-
奈良時代
ならじだい
 A.D.710~794年 ☆日本の歴史の時代の名前 ☆奈良に政治の中心があった。国の法律を作り、仏教を国の宗教と決めた
the Nara Era
A.D.710~794年 ☆日本の歴史の時代の名前 ☆奈良に政治の中心があった。国の法律を作り、仏教を国の宗教と決めた
the Nara Era
-
広まって・広まる
ひろまって・ひろまる
 宗教や習慣や考え方などが遠くの地方まで行って、みんなに知られるようになる
to become known; to spread
広める
宗教や習慣や考え方などが遠くの地方まで行って、みんなに知られるようになる
to become known; to spread
広める
-
避けられる・避ける
さけられる・さける
 [を]
悪いものやよくないことと関係を持たないようにしたり、会わないようにしたりする
to avoid
[を]
悪いものやよくないことと関係を持たないようにしたり、会わないようにしたりする
to avoid
-
現在
げんざい
 今 ☆少し長い時間について言う
at the present day
今 ☆少し長い時間について言う
at the present day
-
再び
ふたたび
 また;もう一度
again
また;もう一度
again
-
調味料
ちょうみりょう
 料理に味をつけるもの (例:しょうゆ、塩、さとう)
a seasoning
料理に味をつけるもの (例:しょうゆ、塩、さとう)
a seasoning
-
(しょう油)であろう
(しょうゆ)であろう
 (しょうゆ)だろう ☆書き言葉
(しょうゆ)だろう ☆書き言葉
-
あることはあるが
あることはあるが
 あるということはほんとうだが、少し違っている点もある
あるということはほんとうだが、少し違っている点もある
-
それぞれ
それぞれ
 一つ一つ、一人一人
each; respectively
一つ一つ、一人一人
each; respectively
-
香り
かおり
 いいにおい
a pleasant smell
いいにおい
a pleasant smell
-
異なる
ことなる
 違う;同じではない
to differ
違う;同じではない
to differ
-
調理
ちょうり
 料理を作ること
cooking
~する
料理を作ること
cooking
~する
-
豆腐
とうふ
 豆から作った、白くて、やわらかい食べ物
tofu; bean curd
豆から作った、白くて、やわらかい食べ物
tofu; bean curd
-
つけたり・つける
つけたり・つける
 [に][を]
つくようにする
to dip (sashimi) into (soy sauce); to put
虫がつく
[に][を]
つくようにする
to dip (sashimi) into (soy sauce); to put
虫がつく

-
和食
わしょく
 日本の料理
Japanese-style food
和服:着物
日本の料理
Japanese-style food
和服:着物
-
なくてはならない
なくてはならない
 [に]
欠かすことができない;ぜひ必要な
[に]
欠かすことができない;ぜひ必要な
-
(しょう油)ほどではない
(しょうゆ)ほどではない
 ~のようには、程度が高く(または、低く)ない
~のようには、程度が高く(または、低く)ない
-
みそ汁
みそしる
 みそで作ったスープ
miso soup
みそで作ったスープ
miso soup

-
(みそ汁)をはじめ
(みそしる)をはじめ
 ~が一番代表的な例で、ほかに・・・・
~が一番代表的な例で、ほかに・・・・
-
煮物
にもの
 野菜や肉、魚などを煮て作った料理
boiled food
野菜や肉、魚などを煮て作った料理
boiled food
-
用いられる・用いる
もちいられる・もちいる
 [を]
使用する
to use
[を]
使用する
to use
-
酢
す

-
ソース
ソース

-
化学調味料
かがくちょうみりょう
 化学的に作った調味料
a chemical seasoning; MSG
化学的に作った調味料
a chemical seasoning; MSG
-
一般的に
いっぱんてきに
 普通
in general
普通
in general
-
あっさりしている
あっさりしている
 味などが薄くて、あまり強くない
(of taste) plain; light
味などが薄くて、あまり強くない
(of taste) plain; light
-
スパイス
スパイス

-
揚げたり・揚げる
あげたり・あげる
 [を]
熱くした、たくさんの油の中に食べ物を入れて、調理する
to deep-fry
[を]
熱くした、たくさんの油の中に食べ物を入れて、調理する
to deep-fry

-
いためたり・いためる
いためたり・いためる
 [を]
フライパン(flying-pan)で油を少し使って、材料をまぜながら、調理する
to stir-fry
[を]
フライパン(flying-pan)で油を少し使って、材料をまぜながら、調理する
to stir-fry

-
新鮮な
しんせんな
 (魚や野菜などが)とれてから、時間がたっていなくて、新しくて、いい
fresh
(魚や野菜などが)とれてから、時間がたっていなくて、新しくて、いい
fresh
-
豊富に
ほうふに
 いいものがたくさん、十分に
abundantly, in plenty
いいものがたくさん、十分に
abundantly, in plenty
-
手に入る
てにはいる
 (欲しいものが)自分のものになる
to become available; to be obtainable
車を手に入れる
(欲しいものが)自分のものになる
to become available; to be obtainable
車を手に入れる
-
基本
きほん
 何かをするときに、一番大切で、ほかのことの中心であるもの
a basis, the basics
何かをするときに、一番大切で、ほかのことの中心であるもの
a basis, the basics
-
したがって
したがって
 だから
だから
-
最も
もっとも
 一番
most
一番
most
-
食卓
しょくたく
 食事のとき、使うテーブル
a dining table
食事のとき、使うテーブル
a dining table
-
料理によって季節を感じる
りょうりによってきせつをかんじる
 季節の特徴のある料理(例えば、春に春らしい材料を使った料理)を食べると、その季節の良さやその季節になったことを感じる
季節の特徴のある料理(例えば、春に春らしい材料を使った料理)を食べると、その季節の良さやその季節になったことを感じる
-
更に
さらに
 その上、もっと
その上、もっと
-
器
うつわ
 食べ物、飲み物、飾る花などを入れるもの
a bowl; a serving dish
食べ物、飲み物、飾る花などを入れるもの
a bowl; a serving dish
-
材質
ざいしつ
 材料の性質
property; quality of the material
材料の性質
property; quality of the material
-
合う
あう
 [に]
二つのものがいっしょにあるとき、ちょうどいい様子になる (例:器が季節に合う[夏は涼しそうな色、冬は暖かそうな色の皿を使う])
to go well; to match
器を季節に合わせる
[に]
二つのものがいっしょにあるとき、ちょうどいい様子になる (例:器が季節に合う[夏は涼しそうな色、冬は暖かそうな色の皿を使う])
to go well; to match
器を季節に合わせる
-
ただ
ただ
 ほかのことは何も関係がなく、それだけ
only, just
ほかのことは何も関係がなく、それだけ
only, just
-
(味)さえ(よけれ)ばいい
あじさえよければいい
 (味)だけ(よけれ)ばいい
(味)だけ(よけれ)ばいい
-
戦前
せんぜん
 戦争の前 ☆日本では特に第二次世界大戦の前を言う
prewar times, the pre-World War II period
戦後
戦争の前 ☆日本では特に第二次世界大戦の前を言う
prewar times, the pre-World War II period
戦後
-
昭和30年代
しょうわさんじゅうねんだい
 昭和30~39年(1955~1964年)の間
in the 30s of the Showa period (1955-1964)
昭和30~39年(1955~1964年)の間
in the 30s of the Showa period (1955-1964)
-
高度
こうど
 程度が高いこと
a high degree
程度が高いこと
a high degree
-
成長
せいちょう
 大きく育つこと
growth
~する
大きく育つこと
growth
~する
-
高度経済成長
こうどけいざいせいちょう
 短い間に、急に経済が高い程度になること
high economic growth
短い間に、急に経済が高い程度になること
high economic growth
-
食生活
しょくせいかつ

-
バラエティー
バラエティー
 たくさんの種類
variety
たくさんの種類
variety
-
富む
とむ
 [に]
たくさんある
to be in large quantity
[に]
たくさんある
to be in large quantity
-
影響
えいきょう
 ~する
~する
-
洋食
ようしょく
 西洋の料理
Western food
西洋の料理
Western food
-
中華
ちゅうか
 中国の(料理)
Chinese food
中国の(料理)
Chinese food
-
豊かに
ゆたかに
 いいものがたくさん、豊富に
plentifully
いいものがたくさん、豊富に
plentifully
-
豚肉
ぶたにく
 豚の肉
pork
豚の肉
pork

-
牛肉
ぎゅうにく
 牛の肉
beef
牛の肉
beef
-
肉類
にくるい
 肉の種類に入るもの
meat
肉の種類に入るもの
meat
-
乳製品
にゅうせいひん
 牛乳から作ったもの (例:バターやチーズなど)
diary products
牛乳から作ったもの (例:バターやチーズなど)
diary products
-
都市
とし
 人口が多く、政治や経済や文化の中心である所
a city
人口が多く、政治や経済や文化の中心である所
a city
-
大都市
だいとし
 大きい都市
a big city
大きい都市
a big city
-
すし
すし
 日本の食べ物;酢で味をつけたご飯を、生の魚などといっしょに食べる日本の料理
sushi; raw fish on vinegared rice
日本の食べ物;酢で味をつけたご飯を、生の魚などといっしょに食べる日本の料理
sushi; raw fish on vinegared rice

-
てんぷら
てんぷら
 魚や野菜を油で揚げた日本の料理
tempura; vegetables or fish dipped in batter and deep-fried
魚や野菜を油で揚げた日本の料理
tempura; vegetables or fish dipped in batter and deep-fried

-
そば
そば
 ☆日本の食べ物
buckwheat noodle
☆日本の食べ物
buckwheat noodle

-
(和食の店)の外に
(わしょくのみせ)のほかに
 ~はわかっているが、~ではないものについても
in addition to
~はわかっているが、~ではないものについても
in addition to
-
フランス
フランス

-
ロシア
ロシア

-
イタリア
イタリア

-
ドイツ
ドイツ

-
スペイン
スペイン

-
メキシコ
メキシコ

-
インド
インド

-
各国
かっこく
 それぞれの国
each country
各地、各大学、各社
それぞれの国
each country
各地、各大学、各社
-
看板
かんばん
 商売のため、店や商品の名前を大きく字や絵でかいて、店の外に出し、客に見せるもの
a signboard
商売のため、店や商品の名前を大きく字や絵でかいて、店の外に出し、客に見せるもの
a signboard
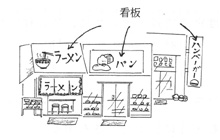
-
手軽に
てがるに
 お金や時間があまりかからないで、簡単に
readily, easily
お金や時間があまりかからないで、簡単に
readily, easily
-
(国際)化
こくさいか
 (外国と関係を持つよう)になること
internationalization
(外国と関係を持つよう)になること
internationalization
-
温室
おんしつ
 寒いときでも野菜や花が育てられるように、中の温度を高くしてあるところ ☆普通はビニールなどで作る
a greenhouse
寒いときでも野菜や花が育てられるように、中の温度を高くしてあるところ ☆普通はビニールなどで作る
a greenhouse

-
~のおかげで
~のおかげで
 ~があるために ☆結果がいいときに使う
~があるために ☆結果がいいときに使う
-
(一年)中
いちねんじゅう
 一年の間ずっと、いつでも
一年の間ずっと、いつでも
-
温めたり・温める
あたためたり・あたためる
 [を]
(ものを)温かくする ☆ものについては「暖かい」ではなく、「温かい」と書く
to warm; to heat
[を]
(ものを)温かくする ☆ものについては「暖かい」ではなく、「温かい」と書く
to warm; to heat
-
すぐ
すぐ
 非常に短い時間で
at once
非常に短い時間で
at once
-
即席
そくせき
 準備をしなくても、すぐできること
impromptu
準備をしなくても、すぐできること
impromptu
-
ラーメン
ラーメン
 中華そば
Chinese noodle
中華そば
Chinese noodle
-
食品
しょくひん
 食料品
food products
食料品
food products
-
インスタント食品
インスタントしょくひん
 即席でできる食品
instant food
インスタント:instant
即席でできる食品
instant food
インスタント:instant
-
冷凍食品
れいとうしょくひん
 冷たく凍らせた食品 ☆長い期間、悪くならない
frozen food
冷たく凍らせた食品 ☆長い期間、悪くならない
frozen food
-
数多く
かずおおく
 たくさん
in large numbers
たくさん
in large numbers
-
フライ
フライ
 油で揚げたもの
fry
油で揚げたもの
fry

-
調理済み
ちょうりずみ
 調理が済んだもの
cooked; ready-made
調理が済んだもの
cooked; ready-made
-
持ち帰り・持ち帰る
もちかえり・もちかえる
 [を]
持って帰る
to carry back; to take ~ home
[を]
持って帰る
to carry back; to take ~ home
-
すぐに
すぐに
 すぐ
immediately
すぐ
immediately
-
盛んに
さかんに
 多くの人に広く利用されて
in wide use
多くの人に広く利用されて
in wide use
-
フライドチキン
フライドチキン

-
ハンバーガー
ハンバーガー

-
ファースト・フード
ファースト・フード

-
待たされる=待たせられる
またされる=またせられる
 「待たせる」+「られる」
「待たせる」+「られる」
-
(変化)につれて
(へんか)につれて
 ~とともに
~とともに
-
時代区分
じだいくぶん
 時代の分け方
the division into periods
時代の分け方
the division into periods
-
原始
げんし
 弥生時代より前の時代
the genesis
弥生時代より前の時代
the genesis
-
縄文時代
じょうもんじだい
 B.C.4世紀より前の時代
the Jomon Period
B.C.4世紀より前の時代
the Jomon Period
-
弥生時代
やよいじだい
 B.C.3世紀~A.D.3世紀
the Yayoi Period
B.C.3世紀~A.D.3世紀
the Yayoi Period
-
古代
こだい
 古墳時代から平安時代まで
ancient times
古墳時代から平安時代まで
ancient times
-
古墳時代
こふんじだい
 A.D.4世紀から8世紀初めまで
the Kofun Period; Tumulus period
A.D.4世紀から8世紀初めまで
the Kofun Period; Tumulus period
-
大和時代
やまとじだい
 A.D.4世紀から8世紀初めまで
the Yamato Period
A.D.4世紀から8世紀初めまで
the Yamato Period
-
奈良時代
ならじだい
 A.D.710~794年
the Nara Period
A.D.710~794年
the Nara Period
-
平安時代
へいあんじだい
 794年から12世紀後半まで
the Heian Period
794年から12世紀後半まで
the Heian Period
-
中世
ちゅうせい
 鎌倉時代から戦国時代まで
the middle ages
鎌倉時代から戦国時代まで
the middle ages
-
鎌倉時代
かまくらじだい
 12世紀後半から14世紀半ばまで
the Kamakura Period
12世紀後半から14世紀半ばまで
the Kamakura Period
-
南北朝時代
なんぼくちょうじだい
 14世紀初め
the period of the Northern and Southern Dynasties
14世紀初め
the period of the Northern and Southern Dynasties
-
室町時代
むろまちじだい
 14世紀初めから16世紀後半まで
the Muromachi Period
14世紀初めから16世紀後半まで
the Muromachi Period
-
戦国時代
せんごくじだい
 15世紀後半から16世紀後半まで
the Warring States period
15世紀後半から16世紀後半まで
the Warring States period
-
近世
きんせい
 安土桃山時代から江戸時代まで
early-modern times
安土桃山時代から江戸時代まで
early-modern times
-
安土・桃山時代
あづち・ももやまじだい
 16世紀後半
the Azuchi-Momoyama Period
16世紀後半
the Azuchi-Momoyama Period
-
江戸時代
えどじだい
 17世紀から19世紀後半まで
the Edo Period
17世紀から19世紀後半まで
the Edo Period
-
近代
きんだい
 明治時代よりあとの時代
recent times
明治時代よりあとの時代
recent times
-
明治時代
めいじじだい
 1868年から1912年まで
the Meiji Period
1868年から1912年まで
the Meiji Period
-
大正時代
たいしょうじだい
 1912年から1926年まで
the Taisho Period
1912年から1926年まで
the Taisho Period
-
現代
げんだい

-
昭和時代
しょうわじだい
 1926年から1988年まで
the Showa Period
1926年から1988年まで
the Showa Period
-
平成時代
へいせいじだい
 1988年から
the Heisei Period
1988年から
the Heisei Period